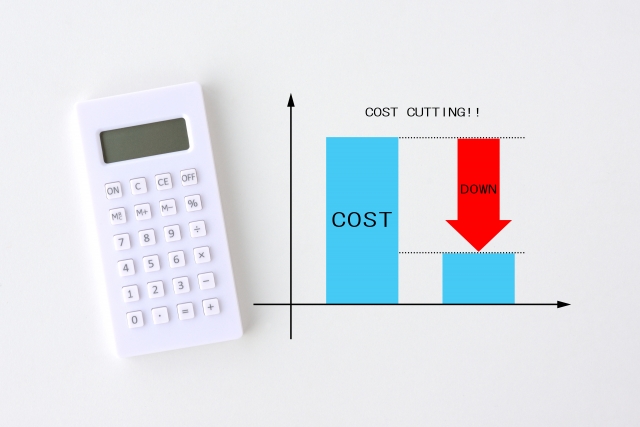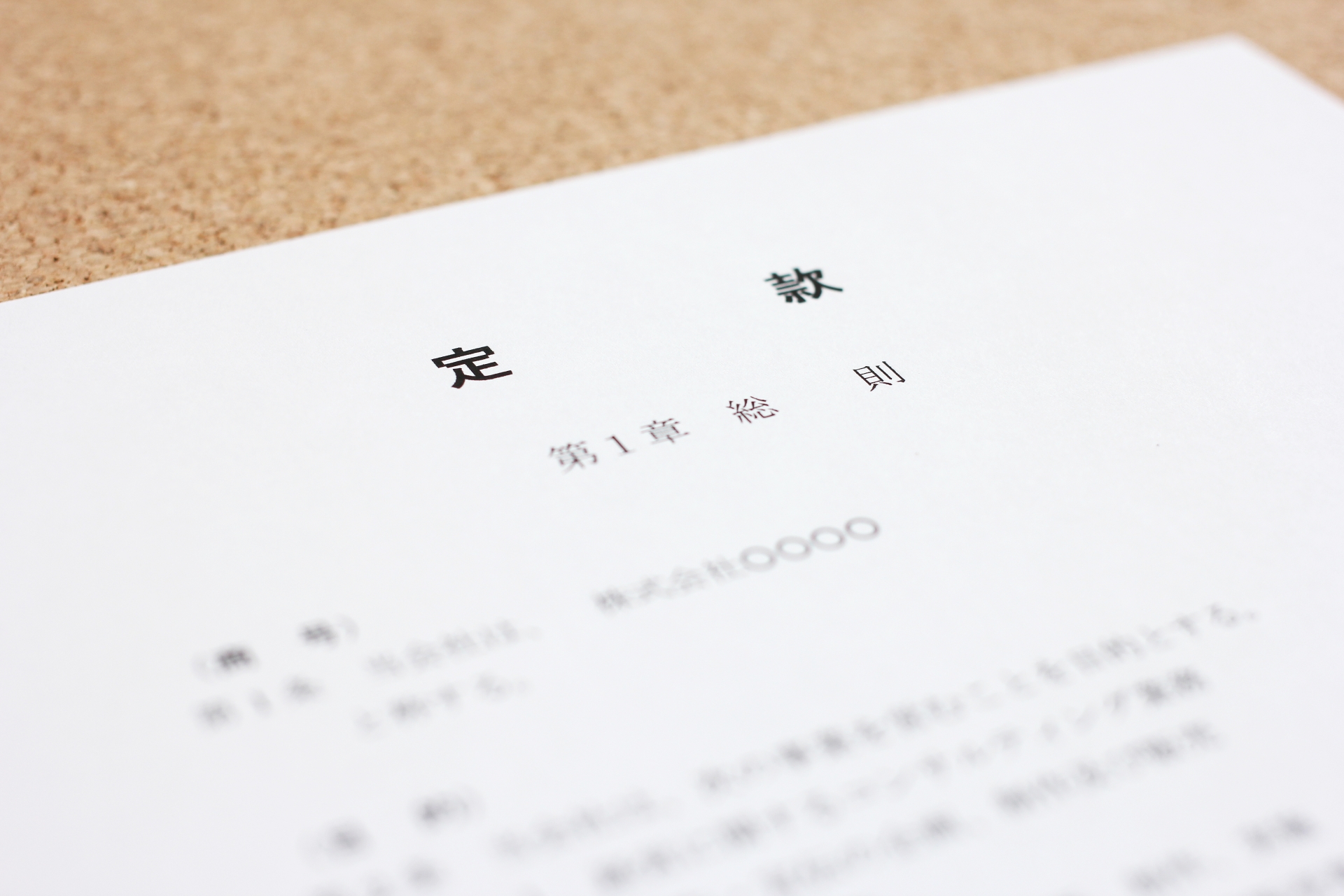当記事では、合同会社の解散・清算に必要となる全手続きについてポイント解説しています。
どんな事業にも始まりがあれば終わりもあります。
事業の終わりは「倒産」という強制的な終わり方だけではありません。
事業の目的が達成されたので法人として継続する必要が無くなった場合や、代表者が年配になったため事業から引退する場合など、いわゆる自主廃業という形もあります。この場合、自主的に法人を解散する手続きをとることになります。
合同会社の解散手続きは法律の則って、適切に行う必要があります。
合同会社という法人格をもって事業を行っていたということは、様々な利害関係者(取引先、債権者、公共機関等)も居たということ。
合同会社の解散手続きは、通常の変更手続きとは異なり、取引先や債権者等への手続きも必要になります。スムーズに解散・清算手続きを行うためにも、手続きの全体像を当ページで把握頂ければと思います。
手続きの流れや必要書類、注意点なども解説しておりますので、ぜひとも参考にしてください。
それでは、どうぞご覧ください。
①合同会社の解散事由
合同会社が解散する場合は法律で決まっており、以下の場合に解散することになります。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 総社員の同意
- 社員が欠けたこと
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
当ページでは、解散事由としては一般的な上記3の「総社員の同意」による解散手続きについて解説します。
合同会社の「社員」とは出資者のことです。
合同会社は、定款に定めた存続期間が満了したり、定款に定めた独自の解散事由が発生したりした場合に解散します。
しかし、定款に存続期間の定めや特別な解散事由を定めていない場合でも、出資者全員の同意さえあれば、合同会社はいつでも解散できるようになっています。
逆に、定款に存続期間を定めておりその期間が満了していない場合であっても、事業の継続が不要だと判断されるなら、出資者全員の同意で解散できるようになっています。
②解散・清算手続きのポイント
3回の登記申請が必要
世間一般的には、「解散手続き」というあいまいな表現をされることが多いのですが、厳密には以下の3回分の登記の手続きが含まれています。
- 解散の登記
- 清算人選任の登記
- 清算結了の登記
実際の手続きとしては、1、2を同時に行うことが一般的ですので、管轄の法務局には 2、3回足を運ぶことになります。
2ヶ月の公告が必要
上記1、2と3の間には、最低2ヶ月間「公告」という手続きを経る必要があります。
つまり、1、2の登記をした直後に、3の登記は行えないということです。最低でも2カ月間官報に公告を掲載します。
解散の登記から清算結了の登記までの一連の手続きには、2ヶ月+αの期間が必要になることを予め理解しておきましょう。
書類の作成や関係者に押印してもらう手配、官報に公告を掲載してもらう手配等に要する期間を考慮すると、全ての手続きが終わるまでには最低でも3ヶ月前後の期間を見積もっておくのが現実的な目安です。
③管轄法務局の場所を確認する
申請先の管轄法務局の場所を予め確認しておきます。
解散・清算手続きに関して不明な点があれば、管轄の法務局で相談します。
管轄法務局で事前相談をした場合には、相談に応じた担当者の氏名を記憶しておくと、再度相談する際に便利です。
管轄法務局の場所が分からない方は、法務局のHP参照してください。
④手続きの流れの全体像
合同会社の解散・清算手続きの流れは次の通りです。
- 総社員による解散の決議
- 解散日の到来
- 清算人の選任
- 清算人の就任
- 解散登記(解散の日から2週間以内)
- 清算人の就任登記(解散の日から2週間以内)
- 遅滞なく、財産目録・貸借対照表の作成
- 官報に公告(2か月以上の期間)
- 債務弁済後に、残余財産を分配する
- 清算事務が終了したら、社員に清算計算の承認を受ける
- 清算結了の登記(社員の承認を受けた日から2週間以内)
- 合同会社の解散・清算登記手続きは全て終了!
⑤総社員による解散の決議
総社員の同意による解散の決議を行い、会社が解散する日付を決めます。
手続きの専門家ではない一般の方が手続きを行う場合は、決議を行った日付と解散する日付を同日にすると分かりやすいです。
決議内容を「総社員の同意書」として書類作成します。
⑥解散日の到来
総社員の同意(決議)で定めた解散の日が到来すると、合同会社は法律上解散状態になります。
しかし、合同会社は「解散」しただけでは法律上消滅しないことになっています。
合同会社を解散した後に、「清算」という手続きをする必要があります。
清算というのは、会社の財産を全て処分してしまうことです。
具体的には以下の1~3を行うことを清算といいます。
- 未回収の債権を全て回収する(取り立てる)。
- 未払いの債務を全て弁済する(支払う)。
- 上記1,2の後で会社に残った財産を、出資者に分配する。
この1~3を全て終わらせると会社の財産はゼロになるので、そこで清算が終わり、会社が正式に消滅することになります。
⑦清算人を選任する
上記1~3の清算を行う人を「清算人」といいます。
解散した合同会社は清算をするために、清算人を選任する必要があります。
合同会社の社員の中から清算人を選任することもできますし、社員以外から清算人を選任することもできます。
清算人は最低1名選任する必要がありますが、必要に応じて2名以上選任することもできます。
清算人を選任する際には、清算人選任決議書を作成します。なお、書類の作成及び法務局の申請に清算人の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が 必要になりますので、予め用意しておきましょう。
⑧清算人が就任を承諾する
清算人を「選任する」ことと、選任された人が「就任を承諾する」ことは、法律上は一応別の話です。
選任されても、就任を拒否することは一応できるからです。
ただし、実際は、清算人を選任する時点で清算人へ就任することへの内諾は事前に得ていることがほとんどだと思われます。
選任された人が、清算人の就任を承諾したことを明らかにするために、就任承諾書を作成します。
就任を承諾した日付をもって、清算人となります。
⑨その他の書類を作成する
登記申請に必要な残りの書類を作成します。具体的には以下の書類になります。
- 合同会社解散及び清算人選任登記申請書
- 別紙
- 印鑑届書
※「別紙」については、テキストファイルで作成した上で、CD-R等に入れて、法務局に提出します。使用可能な磁気ディスクの種類については法務省のHPからご確認ください。
※「印鑑届出書」については、手書きで記入でも全く差し支えありません(「印鑑届出書」の用紙は、法務局の窓口にも置いてあります)。
⑩管轄法務局で解散の登記と清算人選任の登記を申請する
管轄法務局で以下の登記を申請します。
- 解散の登記
- 清算人選任の登記
この1、2は一応別な手続きですが、解散の登記は清算人が申請することになっていますので、実務上は1、2をまとめて管轄法務局に申請します。
以下、法務局での行動手順を説明します。
(1) 申請日当日に必要なもの

- 法務局に登録する法人の実印と清算人の実印(何かあったときに、その場で対応できるので便利)
- ホッチキス、クリッフ゜
- 印紙代3万9千円
- 提出予定の以下の申請書類(必要箇所へ押印済みの書類)
- 合同会社解散及び清算人選任登記申請書
- 総社員の同意書
- 清算人選任決議書
- 清算人の就任承諾書
- 清算人の印鑑証明書
- 印鑑届書
- 別紙のデータが入ったCD-R等
(2) 申請前に相談窓口で最終確認
この時点で既に書類は作成されていると思いますが、直前に相談窓口で書類をチェックしてもらうと良いでしょう。
書類には訂正印が押してあるはずですので、訂正が必要な場合は、その場で訂正できます。
(3) 印紙3万9千円分を購入する
申請書類に問題がなければ、法務局の印紙売り場で登録免許税3万9千円分の印紙を購入して、合同会社解散及び清算人選任登記申請書の余白(申請日の日付の下など)にはってください。
なお、法務局に相談すると、「印紙は別な台紙にはってください」と指導されることがありますが、どちらでもかまいません。
(4) 以下の書類をホッチキスでとめる(左綴じ)
- 合同会社解散及び清算人選任登記申請書
- 総社員の同意書
- 清算人選任決議書
- 清算人の就任承諾書
- 清算人の印鑑証明書
※ 提出する印鑑証明書について
印鑑を届け出る清算人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)のみの提出で足ります。
(5) 他の書類とまとめて窓口に提出
ホッチキスで綴じた書類に、印鑑届書、別紙テ゛ータの入ったCD-R(又はFD)を添えて窓口に提出。クリッフ゜で留めておくとよいでしょう。
(6) 登記完了予定日の確認
登記の完了を法務局から連絡してはくれませんので、提出の際に登記完了予定日を法務局の申請窓口で確認しておきましょう。
何か修正が発生する場合は、登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡があります。
登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡がなければ、通常、登記は完了しているはずです。
⑪財産目録等を作成する
清算人は、その就任後遅滞なく、会社の財産の現況を調査して、会社が解散した日における財産目録及び貸借対照表を作成し、各社員にその内容を通知しなければならなりません。
⑫官報に公告を掲載する
合同会社の解散後は遅滞無く、債権者に対して、一定の期間内(この期間は2ヶ月を下ることはできません)にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。
清算してしまうと最終的には会社がなくなってしまうわけですから、その前に「債権者は名乗り出でください」と呼びかける手続きです。
官報に公告を掲載するには、「独立行政法人国立印刷局」という組織に申し込みをします。
具体的には取次店である最寄りの「官報販売所」に申し込みをするのが一般的です。
申し込み方法は電話・FAX・メール等で可能です。
官報販売所の担当者に「合同会社の解散の公告をしたい」と伝えれば、すぐに分かってもらえます。
官報に公告する原案をこちらで作成して、最寄りの官報販売所にFAXします。
原案を作成したら官報販売所にFAXして、官報販売所の担当者に確認してもらいます。
公告の内容が確定したら、官報の掲載日が決まり次第、官報販売所の担当者から連絡がきます。
なお、官報公告の費用は文字数によって多少増減します。概ね3万数千円程度になります。
⑬債務弁済後に、残余財産を分配する
官報の公告期間(2カ月)が経過したら、債権者に債務を弁済して、残余財産があれば、出資者に分配します。
これで会社の財産がゼロになり清算事務が終了となります。
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定めることになっています。
⑭清算事務が終了したら、社員に清算に係る計算の承認を受ける
清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければなりません。以下の書類を作成します。
- 清算結了承認書
- 清算に係る計算書
⑮管轄法務局で清算結了の登記を申請する
清算に係る計算をして社員の承認を受けてから2週間以内に、管轄法務局で清算結了の登記を申請します。
合同会社清算結了登記申請書を作成し、法務局に提出します。
以下、法務局での行動手順を説明します。
(1) 申請日当日に必要なもの
- 法務局に登録する法人の実印と清算人の実印(何かあったときに、その場で対応できるので便利)
- ホッチキス、クリッフ゜
- 印紙代2千円
- 提出予定の以下の申請書類(必要箇所へ押印済みの書類)
- 合同会社清算結了登記申請書
- 清算結了承認書
- 清算に係る計算書
(2) 申請前に相談窓口で最終確認
既に書類は作成されていると思いますが、直前に相談窓口で書類をチェックしてもらうと 良いでしょう。
書類には訂正印が押してあるはずですので、訂正が必要な場合は、その場で訂正できます。
(3) 印紙2千円分を購入する
申請書類に問題がなければ、法務局の印紙売り場で、登録免許税2千円の印紙を購入して、合同会社清算結了登記申請書の余白(申請日の日付の下など)にはってください。
なお、法務局に相談すると、「印紙は別な台紙にはってください」と指導されることがありますが、どちらでもかまいません。
(4) 以下の書類をホッチキスでとめる(左綴じ)。
- 合同会社清算結了登記申請書
- 清算結了承認書
- 清算に係る計算書
(5) 申請窓口に提出・登記完了予定日の確認
登記の完了を法務局から連絡してはくれませんので、提出の際に登記完了予定日を法務局の申請窓口で確認しておきましょう。
何か修正が発生する場合は、登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡があります。
登記完了予定日(補正日)までに法務局から連絡がなければ、通常、登記は完了しているはずです。
以上で合同会社の解散・清算に関する登記の手続きは終了となります。
自分で出来る!合同会社解散・清算手続きキットのご案内
こちらのマニュアルでは、合同会社の解散・清算手続き手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!
詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社解散・清算手続きキット