
当記事では、福祉(介護)タクシーの運転者についてどのような規定があるのか解説をいたします。
福祉(介護)タクシーの運転者に必要な免許は?
第2種運転免許が必要です。
福祉(介護)タクシーは道路運送法上の一般乗用旅客自動車運送事業に当たりますから、いわゆる4条許可というものが必要になります。
いやいや、ぶら下がり許可の場合は、第2種運転免許が無くても許可が取れるのでは?と勘違いをされている方も多いのですが、これは半分正解で、半分間違っています。
いわゆる「ぶら下がり許可」は、一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業などの許可取得を前提としている制度です。
一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可を受けるには、第2種運転免許を持った運転者が必要になります。
つまり、ぶら下がり許可を取得するにも、第2種運転免許は必要ということになります。
すでに一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者が、新たにぶら下がり許可を受ける場合に限って言うと、第2種運転免許は不要。ということになります。
なかなか説明が難しいところではあるのですが、この辺りの関係性については、非常に込み入った制度設計になっていますので、詳しく知りたいという方は、下の記事も参考にしてみてください。
福祉(介護)タクシーの運転者になれない者とは?
福祉(介護)タクシーの運転者になれない者については、旅客自動車運送事業運輸規則第36条にその規定が設けられています。
次の事項のうち、一つにでも該当する者は、福祉(介護)タクシーの運転者にはなれません。
- 日日雇い入れられる者
- 2月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
- 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
1は、いわゆる「日雇い」でその日に労働契約が終了するような場合です。「日雇い労働者に旅客の運送という責任の重い仕事はさせないでください」ということですね。
2については「2ヶ月以内の短い期間の雇用契約を結んでいる労働者には運転をさせないでください」ということです。
2ヶ月以内ですから、1週間や10日間の雇用契約はもちろん、1ヶ月でもアウトです。
なお、2ヶ月を超える雇用契約期間であればOKです。例えば、3ヶ月の有期雇用契約を結んだ運転者はOKということになります。
3については簡単です。試用期間中の者に旅客の運送はさせないでくださいということ。ただし、14日を超えて引き続き雇用されているものについてはOKということです。2との違いとしては、14日を超えて試用期間中の者ではあるが、雇用契約期間は2ヶ月以上ある労働者ということになります。
4については、勤務形態ではなく、賃金の支払いスパンの問題です。1日ごとに給料の支払いをする場合はもちろん、14日未満ですから10日ごとに給料を支払う契約をしている場合もNGです。
福祉(介護)タクシーの運転者の選任についてはどのような定めがあるか
旅客自動車運送事業運輸規則の第35条に運転者の選任についての規定があります。
「旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない」とありますが、これについては規定の仕方が非常に曖昧です。
事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておおかなければならないとされていますが、十分な数とだけ規定されており、実際に何人の運転者が必要であるかまでの規定はありません。
なお、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」という通達には次のような記載がありますので、参考にしてもらえればと思います。
「事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者」については、事業の実態が千差万別であるため、一概に、統一的かつ定量的な基準を定めることは困難であるが、それぞれの事業者の事業の実態を十分考慮 して、適切な数の運転者を選任するよう指導すること。
つまりは、画一的に決めることはできないので、事業の実態に応じて適切な運転者を選任してくださいということですね。管轄運輸局の裁量に任されているということが言えますね。
ちなみに、福祉(介護)タクシーの許可を取得するには、運転者は最低1名でOKです。また、事業用自動車の数も1台以上あればOKです(一般のタクシー事業者は事業用自動車が最低でも5台以上必要)。
福祉(介護)タクシーの運転者として新たに雇い入れた者についての指導や適性診断について
福祉(介護)タクシー事業者が新たに運転者として雇い入れた者についてはどのような規定があるのでしょうか。
旅客自動車運送事業運輸規則の第36条第2項に規定があります。
福祉(介護)タクシー事業者が新たに雇い入れた運転者については、雇入後少なくとも10日間の指導、監督及び特別な指導を行い、また、適性診断を受けさせた後でなければ運転者として選任してはなりません。
ただし、この新たに雇い入れた運転者が、福祉(介護)タクシー事業者の営業区域内において、雇入れの日前2年以内に通算で90日以上、一般乗用旅客自動車運送事業(※)の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りではありません。
※福祉(介護)タクシー事業者は一般乗用旅客自動車運送事業に分類されています。
ここでいう指導、監督及び特別な指導と適性診断についての該当条文を載せておきますので、これから福祉(介護)タクシー事業の許可を受けて事業を開始しようとしている方、運行管理者に就任する予定の方は、参考にしてください。
旅客自動車運送事業運輸規則の指導、監督及び特別な指導と適性診断についての参考条文
旅客自動車運送事業運輸規則(第38条)
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則(第38条第2項)
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者
四 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
旅客自動車運送事業運輸規則(第38条第4項)
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導をしなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則(第39条)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。
新たに雇い入れた者の事故歴の把握について
福祉(介護)タクシー事業者は、事業用自動車の運転者を新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認していかなければなりません。
福祉(介護)タクシー事業者の運転者には、介護系の資格が必要か?
こちらについては、福祉(介護)タクシー事業に使う自動車の種類によってその要否が異なります。下記ページで詳しく解説しておりますので、参考にしてください。
介護系資格は必ずしも有していなければならないものではありませんが、資格を持っているほうが、福祉(介護)タクシーという事業の特性上、持っているほうが営業上も有利になるのは確実かと思います。


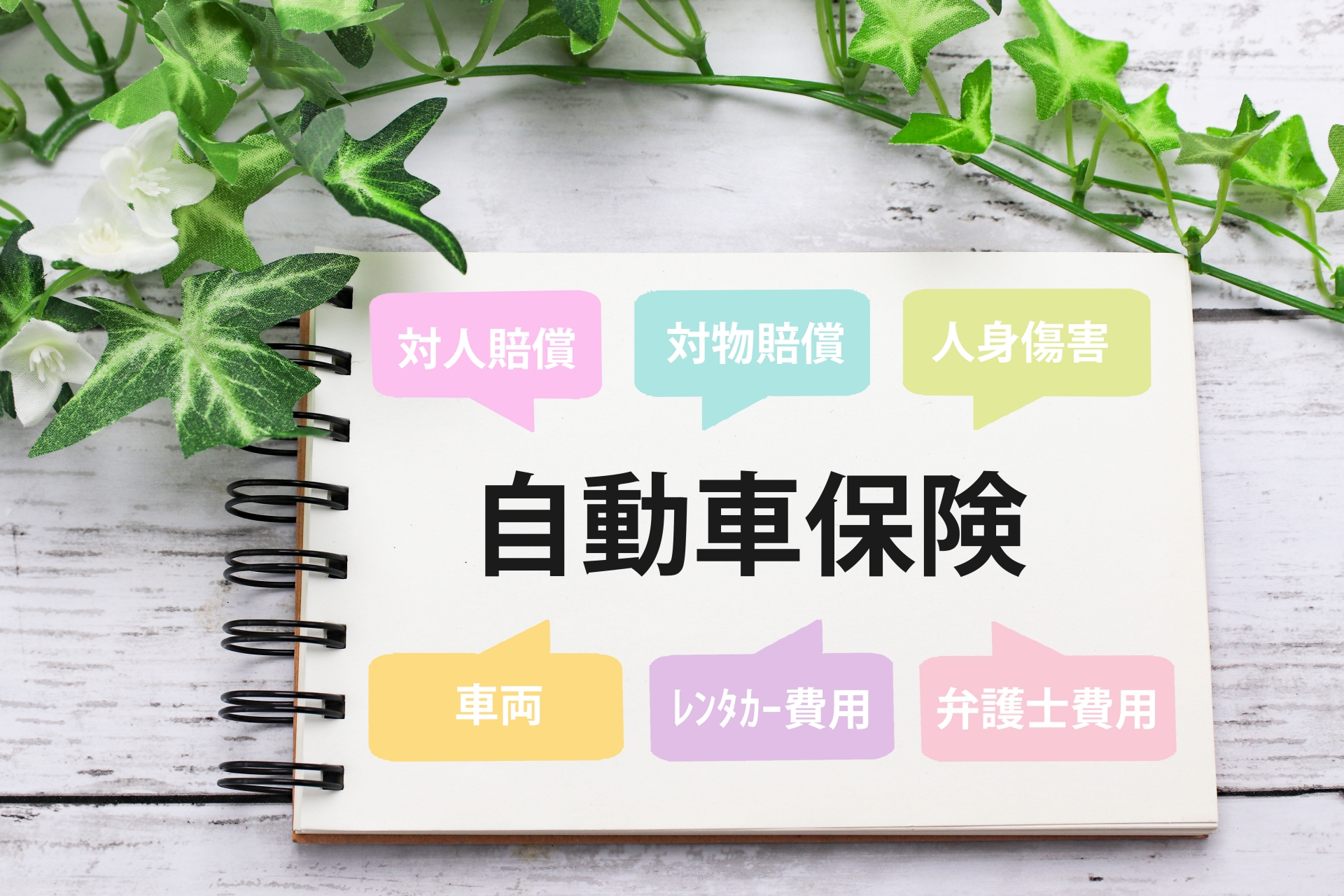

タクシーの許可取得後に行う車両への車体表示について.jpg)


介護タクシー開業サポートオフィスのご案内
介護タクシーの開業をお考えの方へ
行政書士法人MOYORIC(モヨリック)では、介護タクシーの開業をお考えの方に向けて、介護タクシーの許可申請や法人設立、経営革新等認定支援機関による融資サポートを行っております。
ご相談、お見積りは無料です。
どのようなことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。経験豊富な行政書士があなたの疑問にお答え致します。
詳細はこちら。
介護タクシー開業サポートオフィス